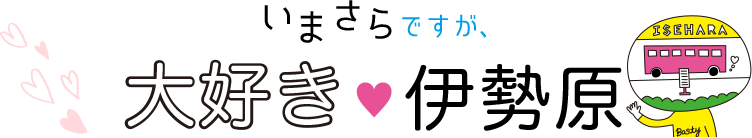大山の木地師が伝える思い
「大山こまの里 金子屋」
木地挽物師 金子吉延さん

大山は木工の材料となる木が豊富なので、昔は椀物などをつくる木地屋がこの辺りに集落をつくっていたんです。江戸時代に大山詣が盛んになると、参拝客のおみやげとして「大山こま」が考案され、こまはよく廻ることから“生活や金運がよく廻る”と、縁起物として人気になりました。
私がこま職人を志したのは、大学を卒業してすぐのことです。もともとは国語教師を目指していましたが、家業を継ぐことに迷いはありませんでした。子どものころから歴代の仕事は見てきましたし、どこに行っても自然と木地玩具に目がいきますからね。昔から心の奥ではやる気だったんだと思います。24歳のときに8代目を継ぎましたので、今年で41年になります。
現在、大山こまの職人は、ほとんどが年配の方ですが、江戸時代からの伝統手法にそれぞれの技術や発想をプラスして、みなさん表情豊かなこまや木地玩具をつくっています。こま職人は道具の刃物をつくる鍛冶仕事から始まって、木の製材、成形・色付けなどの全工程を自分で行うので、こま一つひとつにも作り手の個性が出ますね。
私もこまの形や仕掛けを工夫して、自分自身が新しい発見を楽しみながら、さまざまな新作こまをつくっています。こまを回してお客さんが驚いたり、「面白いね、よく廻るね」と言われると嬉しい。ただそれだけですよ。
大山は夏山祭や紅葉など年中行事もたくさんありますが、参拝客が比較的少なくてゆっくりハイキングできる新緑の季節が特におすすめです。大山を訪れる人々が、伝統工芸の大山こまを通して、この地に息づく歴史や人々の思いも一緒に感じてくれたらいいですね。
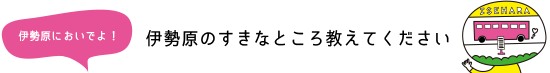
- 伊勢原の好きな場所は?
- もちろん大山です。大山は空気がきれいですよ。
- 伊勢原のおすすめの食べ物は?
- 昔からの製法でつくっている「大山の絹ごし豆腐」ですね。

白くてきれいな肌のミズキの木が、丸みを帯びてつるつるに。工房に並べられた刃物は、金子さんが自分の癖や手の形、削る材料に合わせてすべて自作しています。

木工旋盤(ろくろ)では25センチの特大こまから3ミリのミニこまを製作。くるくる廻る木にバイトという刃物を当てると、あっという間にこまの形が現れます。

木を廻した状態のまま、スラーっと鮮やかな紺と朱の模様が描かれていきます。

『大山こま 台付』
大山こまは麻ひもを芯棒から本体に巻きつけて、飛ばすようにして廻します。喧嘩独楽としても人気で「芯棒が太くて辛抱強い」といわれています。

商標『ひょうたんからこま』
ひょうたんも手づくり。ひょうたんの中に入った3.4ミリの小さなこまもよく廻ります。

『花飾りこま』(上)、『ミニ平こま』(下)
じっくり見るほど面白い、おもちゃ箱のような店内。実は金子さん、毎月のように一点物の創作こまをつくっては、店内の戸棚でこっそり発表しているそうです。

「大山こま参道」の最初にあるのが金子屋支店。お店に隣接してガラス張りの工房があり、運がよければ制作風景を見ることができます(夏場は工房での作業はお休みのことが多いそうです)。

参道を挟んだ向かい側にある民芸調のお休み処は、参道の階段で疲れた身体をお茶や甘味とともに癒やしてくれます。
大山こまの里 金子屋
〒259-1107 神奈川県伊勢原市大山585
TEL:0463-95-2262
大山こまの歴史や金子さんについてもっと知りたい方はコチラ↓
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ooyama/